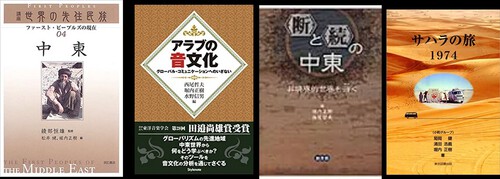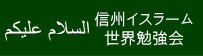e-定例会第30弾をお送りします。e-定例会第30号は、長沢栄治日本学術振興会カイロ研究連絡センター長(前信州イスラーム世界勉強会代表)のカイロ通信第0号「機内映画の感想から」です。
東京大学名誉教授長沢栄治先生には、2024年4月から1年間信州イスラーム世界勉強会代表をお勤めいただきましたが、2025年4月から2年間の予定で、日本学術振興会カイロ研究連絡センター(略称 学振カイロセンター)へセンター長として赴任されました。カイロ在任中お忙しい業務の合間を縫って、カイロ通信不定期連載いただく予定になっています。正式赴任前に執筆いただいた第0回「機内映画の感想から」をe-定例会第30弾としてアップロードしました。エミレーツ航空の機内映画からイスラーム世界の「今」が垣間見えます。
本文はこちらから ☞ カイロ通信0号「機内映画の感想から」
登場する映画
❖ エジプト 「キーラとエル=ギンKeera & Jinn(kīra wa al-jinn)」

カイロ風景
東京大学名誉教授長沢栄治先生には、2024年4月から1年間信州イスラーム世界勉強会代表をお勤めいただきましたが、2025年4月から2年間の予定で、日本学術振興会カイロ研究連絡センター(略称 学振カイロセンター)へセンター長として赴任されました。カイロ在任中お忙しい業務の合間を縫って、カイロ通信不定期連載いただく予定になっています。正式赴任前に執筆いただいた第0回「機内映画の感想から」をe-定例会第30弾としてアップロードしました。エミレーツ航空の機内映画からイスラーム世界の「今」が垣間見えます。
本文はこちらから ☞ カイロ通信0号「機内映画の感想から」
登場する映画
❖ エジプト 「キーラとエル=ギンKeera & Jinn(kīra wa al-jinn)」
(2022年、マルワーン・ハーメド監督作品)
❖ 5か国合作(ヨルダン・フランス等) 「Inshallah a Boy(inshā‘ allāh walad)」
❖ 5か国合作(ヨルダン・フランス等) 「Inshallah a Boy(inshā‘ allāh walad)」
(2023年、アムジャド・アッラシード監督作品)
カンヌ映画祭 the Gan Foundation Award他受賞作
❖ スーダン 「さようならジュリアGoodbye Julia(wadā‘an jūlīyā)」
❖ スーダン 「さようならジュリアGoodbye Julia(wadā‘an jūlīyā)」
(2023年、ムハンマド・コルドファーニー監督作品) アカデミー賞国際映画部門で受賞候補作
❖ エジプト「アル=ゼロ」
❖ エジプト「アル=ゼロ」
(2023年、ムハンマド・ ガマール・アル=アドル監督作品)
❖ パレスチナ「教師 The Teacher (al-ustādhustādh)」
❖ パレスチナ「教師 The Teacher (al-ustādhustādh)」
(2023年、ファルハーン・ナブルーシー監督作品)

2025年度最初のe-定例会は、富永智津子元宮城学院女子大学教授による資料紹介「イスラーム法が活きて働いていた19世紀末の東アフリカ」です。ソマリア南部の町ブラヴァ(Brava)でみつかった19世紀末の民事法廷の裁判記録のご紹介です。通常ではなかなか知ることができないインド洋貿易の拡がり、奴隷貿易や女性の権利と役割等,当時のブラヴァの人々の生活を垣間見せてくれる資料です。
ガザのパレスチナ人の移住先としてトランプ大統領が挙げたソマリア、もちろんそこにも人々の営みがあります。富永先生が描かれたみずみずしいイラストと写真も併せて掲載いたします。



ケニア沿岸ラム島の景観
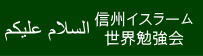
ガザのパレスチナ人の移住先としてトランプ大統領が挙げたソマリア、もちろんそこにも人々の営みがあります。富永先生が描かれたみずみずしいイラストと写真も併せて掲載いたします。
【資料紹介「「イスラーム法が活きて働いていた19世紀末の東アフリカ」】の本文はこちらから

ザンジバルのストーンタウン(世界遺産)と子供たち


ケニア沿岸ラム島の景観
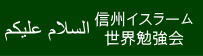
e-定例会(号外)は、深刻な状況にあるガザの状況を踏まえ、The Huffington Post Japan,に2014 年11 月12 日 投稿された、
『終わることのないパレスチナ紛争の根因:それをどう正すか ペーター・コーヘン Peter Cohen』(板垣雄三 訳)と 『コーヘン提案をどう読むか 板垣雄三』 を掲載します。2014年イスラエルのガザ地区への地上侵攻を受けて投稿された論考ですが、9年前に既に今日の危機が予測され、いかに解決に導くかが模索されています。
ペーター・コーヘンは元アムステルダム大学教授の社会学者で、第二次世界大戦を生きのびたユダヤ系オランダ人でもあるとのこと。
深く憂い、考えさせられる論考です!
こちらをクリック
『終わることのないパレスチナ紛争の根因:それをどう正すか ペーター・コーヘン Peter Cohen』(板垣雄三 訳)と 『コーヘン提案をどう読むか 板垣雄三』 を掲載します。2014年イスラエルのガザ地区への地上侵攻を受けて投稿された論考ですが、9年前に既に今日の危機が予測され、いかに解決に導くかが模索されています。
ペーター・コーヘンは元アムステルダム大学教授の社会学者で、第二次世界大戦を生きのびたユダヤ系オランダ人でもあるとのこと。
深く憂い、考えさせられる論考です!
こちらをクリック
☞ 『終わることのないパレスチナ紛争の根因:それをどう正すか ペーター・コーヘン Peter Cohen』
同時にお読みください
同時にお読みください
信州イスラーム世界勉強会事務局です。
9月9日の定例会「世界の中の日本の「中東・イスラーム報道」、豊崎アリサ監督「Caravan to the Future]上映会+トークショーのふたつのイベントは両イベント共、おかげさまで「満員御礼」の大盛況でした。信州イスラーム世界勉強会会員、地元有志の皆さんはもとより、中東報道の第一線に携われているジャーナリスト、遠来の専門家の皆様と、実に多様なお立場の方に参加いただき、それぞれ『パネルはもちろん参加者全体が、あくまでメディア一般の問題として考え合い学び合おうとした。』実に刺激的な【対話集会】となりました。板垣雄三信州イスラーム世界勉強会代表のご参加の皆さまへの御礼のメッセージと当日の「対話のための参考資料」、「要綱・メッセージ・発言資料」を掲載し、御礼とさせていただきます。、

信州イスラーム世界勉強会2023 9 9の行事*を終えて
*対話集会「世界の中の日本の中東・イスラーム報道〈これまで〉と〈これから〉」
同日午前の記録映画Caravan to the Future 上映会に続いての
1月28日夜 松本の‘Caféれら’での会話からはじまった企画が、足掛け7ヵ月+旬日の準備期間にいろいろと枝葉を伸ばして実を結び、長く記憶されるであろう国際報道めぐる市民の対話集会&映画上映会としてめでたく開催されるに到った。
(中略)
集会の内容は、塩交易の歴史や物づくりの伝統や直面するエネルギー危機を自覚する信州という地域(場)において、文化・文明の悠久の展開に関わる視野のもと、日々激動する国際政治経済の動態把握とも密接に関連させながら、学術研究の動向や学校教育の最前線や社会の世界認識の問題点を参照しつつ、メディアの現場と市民との間の率直な対話を深めようとする、多面的で意欲的な試みであった。
(中略)
提言・メッセージ・発言・指摘・応答・共感の凝集こそ、本集会が挙げた成果である。
午前の映画・トークも新鮮で感銘深いものであったが、午後の集会でも、発言者各自が言うべきと信じることを言うと同時に、聴く者は語られることの積極面を探り当てようとし、自らの賛否の立場は自覚しつつも話者の言辞のまじめさや情熱には拍手を送るといった「対話」精神が横溢する雰囲気があった。特定新聞の取り沙汰が浮上しても、パネルはもちろん参加者全体が、あくまでメディア一般の問題として考え合い学び合おうとした。問題の指摘に際して不毛な非難・反駁の応酬など無く、爽快な「対話」フォーラムが出現していた。
9月9日の定例会「世界の中の日本の「中東・イスラーム報道」、豊崎アリサ監督「Caravan to the Future]上映会+トークショーのふたつのイベントは両イベント共、おかげさまで「満員御礼」の大盛況でした。信州イスラーム世界勉強会会員、地元有志の皆さんはもとより、中東報道の第一線に携われているジャーナリスト、遠来の専門家の皆様と、実に多様なお立場の方に参加いただき、それぞれ『パネルはもちろん参加者全体が、あくまでメディア一般の問題として考え合い学び合おうとした。』実に刺激的な【対話集会】となりました。板垣雄三信州イスラーム世界勉強会代表のご参加の皆さまへの御礼のメッセージと当日の「対話のための参考資料」、「要綱・メッセージ・発言資料」を掲載し、御礼とさせていただきます。、

信州イスラーム世界勉強会2023 9 9の行事*を終えて
*対話集会「世界の中の日本の中東・イスラーム報道〈これまで〉と〈これから〉」
同日午前の記録映画Caravan to the Future 上映会に続いての
信州イスラーム世界勉強会代表 板垣雄三 記 (2023 / 9 /11)
1月28日夜 松本の‘Caféれら’での会話からはじまった企画が、足掛け7ヵ月+旬日の準備期間にいろいろと枝葉を伸ばして実を結び、長く記憶されるであろう国際報道めぐる市民の対話集会&映画上映会としてめでたく開催されるに到った。
(中略)
集会の内容は、塩交易の歴史や物づくりの伝統や直面するエネルギー危機を自覚する信州という地域(場)において、文化・文明の悠久の展開に関わる視野のもと、日々激動する国際政治経済の動態把握とも密接に関連させながら、学術研究の動向や学校教育の最前線や社会の世界認識の問題点を参照しつつ、メディアの現場と市民との間の率直な対話を深めようとする、多面的で意欲的な試みであった。
(中略)
提言・メッセージ・発言・指摘・応答・共感の凝集こそ、本集会が挙げた成果である。
午前の映画・トークも新鮮で感銘深いものであったが、午後の集会でも、発言者各自が言うべきと信じることを言うと同時に、聴く者は語られることの積極面を探り当てようとし、自らの賛否の立場は自覚しつつも話者の言辞のまじめさや情熱には拍手を送るといった「対話」精神が横溢する雰囲気があった。特定新聞の取り沙汰が浮上しても、パネルはもちろん参加者全体が、あくまでメディア一般の問題として考え合い学び合おうとした。問題の指摘に際して不毛な非難・反駁の応酬など無く、爽快な「対話」フォーラムが出現していた。
(中略)
報道のプロも大衆も共に市民感覚で取り組んだ「市民・メディアの対話実験」として、記録されてよい集まりだったと自負できよう。配布資料は、集会終了後も、繰り返し眺め考える材料として活用されることが望まれる。この種の集会が世の潮流となることも。了
「信州イスラーム世界勉強会2023.9.9の行事を終えて」の全文はこちらから

報道のプロも大衆も共に市民感覚で取り組んだ「市民・メディアの対話実験」として、記録されてよい集まりだったと自負できよう。配布資料は、集会終了後も、繰り返し眺め考える材料として活用されることが望まれる。この種の集会が世の潮流となることも。了
「信州イスラーム世界勉強会2023.9.9の行事を終えて」の全文はこちらから

繰り返し眺め考える材料として活用されることが望まれる「配布資料」はこちらから!
≪コンテンツ≫
【20230909 対話のための参考資料】
■【国際ジャーナリズムの原点】
「グローバルサウス」の弱み─欧⽶に報道依存、⾃前発信が課題
■ 中東史のプリズムで見るウクライナ紛争
■ 中東・イスラーム報道の〈これまで〉: 前史メモ
■ UNESCOレポート「報道は公共財である」
時事通信社解説委員 杉⼭⽂彦
■ 中東史のプリズムで見るウクライナ紛争
早稲田大学地域・地域間研究機構 招聘研究員/京都大学博士 若林啓史
■ 中東・イスラーム報道の〈これまで〉: 前史メモ
信州イスラーム世界勉強会代表 板垣雄三
■ UNESCOレポート「報道は公共財である」
UNESCO’s Global Report 2021/2022 Short Summary
【対話集会 中東・イスラーム報道 要綱・メッセージ・発言資料】
対話集会に寄せられた提言メッセージ
■ 信州イスラム世界勉強会へのメッセージ 2023/9/9
■ 「対話集会・世界の中の日本の「中東・イスラーム」報道-【これまで】と【これから】」に寄せて
■ メッセージ「白い杖の留学生」に激励を!支援を!
■ 中東・イスラム圏報道対話集会へのメッセージ
発言資料
パネル発言
■「グローバルサウスの弱み」背景と克服への課題
■ 中東・イスラーム報道対話集会資料(2023年9月9日)
提言A これまで
■ 陸上自衛隊のサマーワ派遣 イラクの人々はどうみたか
坂東真理子(昭和女子大学総長、元埼玉県副知事、内閣府男女共同参画局長)
■ 「対話集会・世界の中の日本の「中東・イスラーム」報道-【これまで】と【これから】」に寄せて
林佳世子(東京外国語大学学長 TUFS Media :中東アジア諸国の報道の和訳紹介)
■ メッセージ「白い杖の留学生」に激励を!支援を!
石渡博明(国際視覚障害者援護協会理事長)
■ 中東・イスラム圏報道対話集会へのメッセージ
石川文洋(報道写真家)
発言資料
パネル発言
■「グローバルサウスの弱み」背景と克服への課題
時事通信社解説委員 杉山文彦
■ 中東・イスラーム報道対話集会資料(2023年9月9日)
朝日新聞編集委員 石合 力
提言A これまで
■ 陸上自衛隊のサマーワ派遣 イラクの人々はどうみたか
イスラエル・パレスチナ 歴史的和平合意から30年
提言B これから
■ 歴史実践の主体を育てる世界史授業のために
NHK解説主幹 出川 展恒
提言B これから
■ 歴史実践の主体を育てる世界史授業のために
長野県伊那弥生ケ丘高等学校教諭 小川 幸司
2023/06/29
信州イスラーム世界勉強会のe-定例会の連載企画「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」の連載第9回「イスラーム社会の仕組みとバイアについて」と最終回連載第10回「つれずれなるまままに」にをおとどけします。
第8回で堀内センセの中東のフィールドワークの旅も終了しましたが、連載第9回は中東フィールドワークの旅から得られたイスラーム社会の仕組み、平等と公正な精神によって支えられるイスラーム法(シャリーア)について語られます。そして、アフリカ〜地中海〜中東〜中央アジア〜インド〜東南アジア〜中国の「広域社会」に住む人々をつなぎ、宗教や境界をも超える力をもつ「バイア」について、広域世界を俯瞰した視座で語られます。
☞ 「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義連載第9回」の本文はこちらから
第10回は「つれづれなるままに」。全9回の講義踏まえ、堀内センセがが縦横に語ります。
文中考察されているニューカレドニアのアラブ人村については、e‐定例会第25弾は、佐藤幸男富山大学名誉教授の『<文明>と<野蛮>の交差路としての太平洋:ニューカレドニア・アラブ人の「静かなる痛み」とその生活世界』でも登場しました。
第8回で堀内センセの中東のフィールドワークの旅も終了しましたが、連載第9回は中東フィールドワークの旅から得られたイスラーム社会の仕組み、平等と公正な精神によって支えられるイスラーム法(シャリーア)について語られます。そして、アフリカ〜地中海〜中東〜中央アジア〜インド〜東南アジア〜中国の「広域社会」に住む人々をつなぎ、宗教や境界をも超える力をもつ「バイア」について、広域世界を俯瞰した視座で語られます。
☞ 「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義連載第9回」の本文はこちらから
第10回は「つれづれなるままに」。全9回の講義踏まえ、堀内センセがが縦横に語ります。
文中考察されているニューカレドニアのアラブ人村については、e‐定例会第25弾は、佐藤幸男富山大学名誉教授の『<文明>と<野蛮>の交差路としての太平洋:ニューカレドニア・アラブ人の「静かなる痛み」とその生活世界』でも登場しました。
貴重な講義ノートをご提供いただいた堀内正樹先生に改めて御礼申し上げます。
バックナンバーはこちらから
「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第8回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第7回
「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第6回
「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第5回
「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第4回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第3回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第2回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第1回
ご紹介と御礼/自己紹介.pdf へのリンク
バックナンバーはこちらから
「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第8回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第7回
「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第6回
「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第5回
「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第4回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第3回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第2回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第1回
ご紹介と御礼/自己紹介.pdf へのリンク
大変お待たせしました。堀内正樹先生の「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」の連載第6回をお届けします!堀内先生の2020年の早稲田大学での講義録です。エジプト、シナイ半島のベトウィン調査に即して、「方法論的全体主義(Theoretical Wholism)」や「構造主義」が批判的に語られます。
~本文より~
現場で書き取ったフィールドノートを埋めているたくさんのバラバラな事柄の多くは「報告」には拾い上げられずに、放置されたままになっています。音楽のこと、魚取りのこと、造船のこと、菜園の作り方、薬草のこと、料理や食材、排便のしかた、下ネタ、噂話・・・。(中略)こうした事柄は本当はひじょうに豊かな情報なのですが、あまりにも具体的かつ個人的であるためにテーマ化するのが難しいのです。(中略)こうしたジレンマはシナイ調査に限らず、他でもいつも経験してきました。残念なことに、こうした豊かな事柄は「残余経験」のほうに入ってしまうんですよね。
では「それじゃだめだ」となったとき、どういう報告(民族誌)が書けるのか。それについては次回以降モロッコでのフィールドワークをお話しするときに考えてみることにしましょう。
春めいてきた休日午後の読書に最適です。お楽しみください!
本文はこちらから
バックナンバーはこちらから

ハマーダ族の部族会議
1992年 8月 第2次調査より
堀内正樹先生の「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」の連載第4回をお届けします!堀内先生の2020年の早稲田大学での講義録です。今回は、地図作成のお話。地図作成~凡例の話題から、「基礎数学」~「構造主義」~「直観主義数学」~ヴィトゲンシュタインからアラン・チューリングへ、講義内容は壮大に展開します。是非、ご一読ください。
本文はこちらから
☞ 「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第4回
バックナンバーはこちらから
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第3回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第2回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第1回
本文はこちらから
☞ 「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第4回
バックナンバーはこちらから
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第3回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第2回
「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第1回
❖ 来る1月28日(土)14時より松本市の信毎メディアガーデンで、レクチャーコンサート「クルド音楽の誘いーレクチャーと演奏」が開催されます。参加無料・どなたでも参加いただけるレクチャーコンサートです。詳しい情報とお申し込みは、勉強会のサブブログ「イベントニュース」から ☞ 信州イスラーム世界勉強会 イベントニュース (naganoblog.jp)
関連ツイッター ☞ 日本中東学会 JAMES
関連FACEBOOK ☞ 信毎メディアガーデン
信州イスラーム世界勉強会2023年最初の企画(e‐定例会第25弾)は、佐藤幸男富山大学名誉教授の『<文明>と<野蛮>の交差路としての太平洋:ニューカレドニア・アラブ人の「静かなる痛み」とその生活世界』です。佐藤先生ご自身による解説「イスラーム世界への窓~<文明>と<野蛮>の交差路としての太平洋 自己解題」も併せて掲載しています。天国に一番近い島「ニューカレドニア」の秘められた歴史とニューカレドニア・アラブ人の静かな痛み。混迷の世界情勢とも響き合う論考です!

❖ 『<文明>と<野蛮>の交差路としての太平洋:ニューカレドニア・アラブ人の「静かなる痛み」とその生活世界』の本文はこちらから
❖ 『イスラーム世界への窓~<文明>と<野蛮>の交差路としての太平洋 自己解題』はこちらから
○●○●○●○● 佐藤幸男先生 略歴 ○●○●○●○●
佐藤幸男(さとうゆきお)
1948年東京生まれ、暁星高校卒。明治大学政治経済学部卒、明治大学大学院政治経済学研究科修了。
1979年、広島大学総合科学部(平和科学研究センター)講師、名古屋大学大学院法学研究科助教授を経て、
1995年より富山大学教育学部教授、富山大学大学院教育学研究科教授。富山大学人間発達科学部教授、
富山大学大学院人間発達科学研究科教授、富山大学大学院芸術文化研究科教授を歴任。
2013年定年退職(富山大学名誉教授)。
現在は、早稲田大学総合学術研究機構平和学研究所招請研究員ならびに広島大学平和センター客員研究員。
2018年より長野県軽井沢町に転居し、現在は長野県民、信州イスラーム世界勉強会会員。
専門領域:第三世界論、平和研究、アジア太平洋国際関係史。
関心分野:植民地主義論、ニューカレドニア研究、群島世界論。
主な著作:
『世界史のなかの太平洋』(編著)国際書院
『ローカルと世界を結ぶ』(酒井啓子編グローバル関係学7)岩波書店
『<周辺>からの平和学』昭和堂など
筆者近影(ニューカレドニアにて)
堀内正樹先生の「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」の連載第2回をお届けします!堀内先生の2020年の早稲田大学での講義録です。いよいよ中東の旅が始まります。
第1部は
第2部は
第1部は
バグダード~カナキン(イラク)から、イラク・イラン国境を超える旅(1972年1月) イラン・イラク戦争以前の両国国境線を超えるスリリングな旅です。
第2部は
日本人の若者4人が愛車「赤坂小町」号を駆って、ドイツミュンヘンからケニアのナイロビ迄4か月間のわたる車中泊の旅を背景にしたお話(1974年9月末~1月末)。旅について、「報告」について、「事実」について、旅に考えさせられたことの記録です。
サハラ砂漠で砂に埋もれた「赤坂小町号」 1974年(本文より)

本文はこちらから ☞ 「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第2回
連載第1回はこちらから ☞ 「中東の旅から―堀内センセのわせだ講義」連載第1回

堀内正樹先生の「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」の連載第1回をお届けします!堀内先生の2020年の早稲田大学での講義録です。
第1回は旅の準備「フィールドワークって何なんだ?」広くて深くパノラミックなフィールドをお楽しみください!
連載開始にあたって、信州イスラーム世界勉強会 板垣雄三代表の「ご紹介と御礼」、堀内正樹先生の「自己紹介」を11月19日付Blogに掲載しています。画面を☟にスクロールしてご覧ください。
☞ 「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第1回はこちらから!
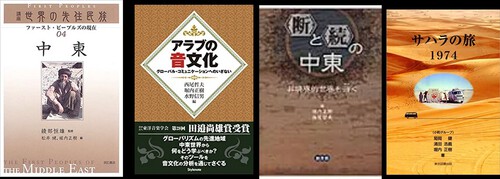
第1回は旅の準備「フィールドワークって何なんだ?」広くて深くパノラミックなフィールドをお楽しみください!
連載開始にあたって、信州イスラーム世界勉強会 板垣雄三代表の「ご紹介と御礼」、堀内正樹先生の「自己紹介」を11月19日付Blogに掲載しています。画面を☟にスクロールしてご覧ください。
☞ 「中東の旅からー堀内センセのわせだ講義」連載第1回はこちらから!